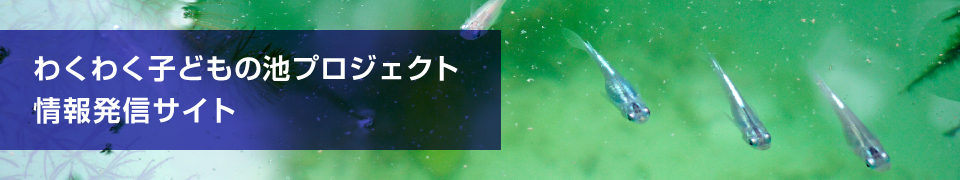
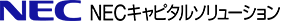
「わくわく子どもの池プロジェクト」の内容
自然の生態系の仕組みを体験的に学ぶことができる授業を、当社グループ会社のボランティアメンバーとNPO法人アサザ基金のメンバーが学校に伺い、ご提供します。
子どもたちが、学校周辺の環境を調べたり、生きものの食物連鎖や生物多様性について学ぶ中で、「どのようなビオトープを作りたいか」を子供たち自身で考え設計し、実際の造成作業を行います。
また造成後には日を改めて、フォローアップの授業を1回行います。
プロジェクトの流れ
ビオトープ造成を希望する学校へプロジェクト内容の説明 |
↓ |
学校設備、周辺環境の下見、詳細設計 |
↓ |
子ども達への環境教育、ビオトープ造成(※) |
↓ |
ビオトープ観察、管理、(フォローアップ授業) |
※基本的なコースでは、「導入授業」「周辺探索(校外観察)」「ビオトープ設計」「ビオトープ造成」の4回の授業を行います(ご要望に応じてフォローアップ授業も実施できます)
授業期間は、おおよそ3~4か月程度を見込んでおります。
プロジェクトの実施例
1.生きものとお話ししよう
生きものの体のつくり、くらし、すみかを中心に当社のボランティアとアサザ基金スタッフが学校で授業を行います。


2.周辺地域探索(校外観察)
自分たちの学校周辺にどんな生きものがいるのかを子どもたち自身が探し・触れ合い・観察することで、周辺に住む生きものたちが来てくれるビオトープ造成を目指します。

3.生きものの立場からビオトープを考え、提案する
これまでの授業で習ったことを活かし、ビオトープの形や場所、生きものに必要な環境要素を子どもたち自身が考え、ビオトープを設計して提案・発表します。

4.設置場所を決める
日なた、日かげなどの様々な環境要素を配慮して決めます。

5.穴を掘る
サイズや土の固さによっては重機を使用して掘る事もありますが、小学生の力だけでも掘りきることができます。深さは一番深いところで40センチ程度です。


6.シートをしく
穴を掘ったらビオトープの水が漏れないようにビニールシートを敷きこみます。シートは2枚重ねて敷きます。

7.土と水を入れる
穴全体に土を均等に入れます。この時に小さい石などがあれば、みんなで取り除きます。土入れが終わったら水を入れます。(水道水で構いません)

8.植物を植え、生きものを入れる
水の中やビオトープの土手となる部分に水草を植え、地元のタニシやメダカを放します。


9.ビオトープの完成
一連の作業を終え、ひとまず完成です。

10.ビオトープに生きものを呼ぼう
ビオトープ完成後は、子どもたちがビオトープの生きものを観察したり、また水面を広げるために草抜きをしたりなど、様々な形で活用できます。また、必要に応じてフォローアップ授業を行います。

写真、文章提供 NPO法人アサザ基金